御嵩町 歴史文化
岐阜県御嵩町に位置する大寺山 願興寺(がんこうじ)は、弘仁6年(815年)に創建された歴史深いお寺で、天台宗の寺院として知られています。その通称「蟹薬師」の由来や、多くの重要文化財を有することから、多くの参拝者や歴史愛好家が訪れるスポットとなっています。
「蟹薬師」の由来
願興寺が「蟹薬師」と呼ばれるようになったのは、とある伝説から。
ある時、村人が大きな蟹に襲われ、命の危機に瀕していました。その際、薬師如来に祈りを捧げたところ、蟹が静かになり、村人は無事に助かったと伝えられています。この出来事から、願興寺は「蟹薬師」として親しまれるようになりました。
重要文化財と建築
願興寺の本尊である薬師如来坐像をはじめ、四天王像、阿弥陀如来立像など、24体もの国指定重要文化財を所蔵しています。
また、明智光秀の重臣であった可児吉長(通称:可児才蔵)は、大寺山 願興寺で生まれ、この地で幼少期を過ごしたと伝えられています。


現在の願興寺本堂は1581年(天正9年)に再建されたものです。本堂は正面の柱間が七間、奥行の柱間が五間の規模の大きい仏堂です。多くの住民や職人が手掛けたことで「四周一間通り」という天台寺院と真宗寺院の混在したような独特な寺院建築ができ上がりました。2017年から本堂の大規模解体修理工事が行われています。


大寺山 願興寺に残る「大寺記」には、約800年前、現在の鬼岩(御嵩町次月・瑞浪市日吉地内)に関の太郎という鬼が住んでいたと伝えられており、近隣の村や町に降りては神出鬼没な不思議な術で乱暴な悪さをしていたそうです。
困り果てた町民たちは、願興寺の本尊・薬師如来に祈りました。関の太郎は薬師如来の力で術が使えなくなり、討ち取られてしまいます。その首を首塚に入れて京へ運ぼうとしましたが、しばらくすると急に重くなり、持てなくなってしまったため、仕方なくその場所に首を埋めて塚をつくりました。現在でも鬼の首塚は残っており、地元の方々によって守られています。
大寺山 願興寺は、その歴史的価値や数々の重要文化財、そして地域に伝わる伝説など、多くの魅力を持つ寺院です。訪れることで、日本の歴史や文化、そして地域の人々の信仰心に触れることができます。
住所(願興寺):岐阜県可児郡御嵩町御嵩1377-1
住所(鬼の首塚):岐阜県可児郡御嵩町中
TEL:0574-67-0386
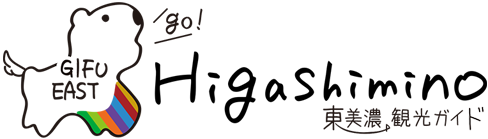
 イベント情報
イベント情報 観光スポット
観光スポット モデルコース
モデルコース